ブランドセーフティ対策とは?対策方法や媒体ごとに対策についても紹介
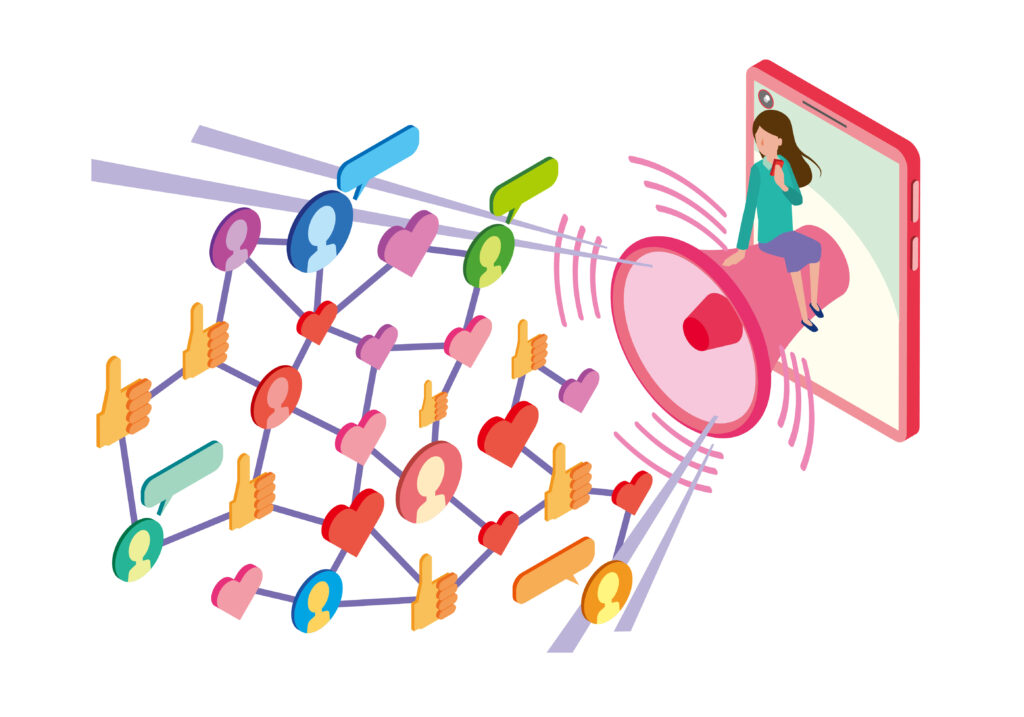
広告出稿によるブランド毀損を少なくするためには、ブランドセーフティ対策が重要です。
この記事では「ブランドセーフティ対策」について解説していきます。結論、ブランドセーフティ対策は企業の価値向上にも直結しやすいです。
広告を検討する際、わかりづらい「ブランドセーフティ対策」を調査した結果をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「ブランドセーフティ対策」の説明や、「ブランドセーフティ対策をするメリット」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んでブランドセーフティ対策について知っていただければ幸いです。
また「ブランディング」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
ブランドセーフティとは?

「ブランドセーフティ」とは、ブランドの広告が不適切なサイトで表示されることを防いで、ブランド毀損にならないように対策することを指す言葉です。
ブランド毀損とは、デジタル広告の発達とともに生まれた言葉ですが、掲載したサイトによってブランドのイメージが下がってしまうことを言います。例えば、違法サイト・過激なサイト・ブランドのイメージとかけ離れた内容を発信しているサイトに広告が掲載されると、一部の消費者を不快にさせたり、ネットで悪い炎上をする可能性があります。
そこで、ブランドセーフティを取り入れることで、ブランド価値を毀損する可能性のある不適切なサイトに掲載することを避けて、ブランドを守ることが可能です。
ブランドセーフティ対策の方法とは?
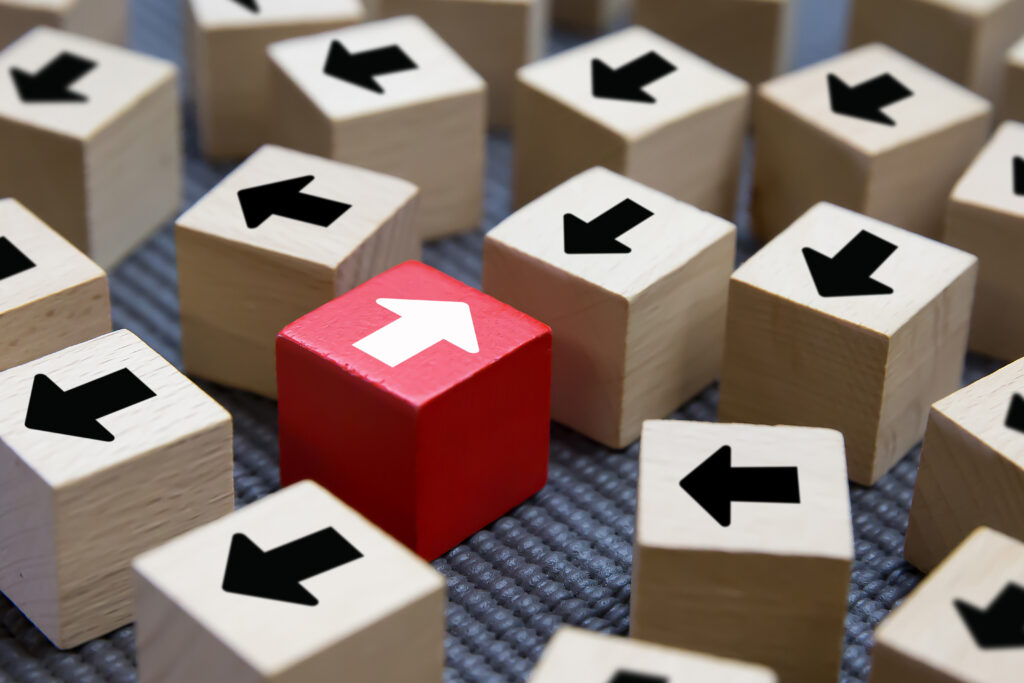
ブランドセーフティ対策の方法は、以下のとおりです。
- プレースメントターゲティングをする
- 信頼できるメディア媒体のみに配信する
- 広告代理店の配信先を自社でも精査する
- プレイベートマーケットプレイスを利用する
それぞれの対策方法を見ていきましょう。
プレースメントターゲティングをする
「プレースメントターゲティング」とは、YouTubeやGoogle、Yahoo!などのネットワーク上で、広告を掲載するサイトや動画コンテンツを手動で選択することです。
本来の目的としては、広告効果を高めるためとされています。
例えば、アウトドアのアパレルブランドがデジタル広告を出す場合、不特定多数のサイトに掲載するのではなく、アウトドア情報を発信しているサイトやキャンプ系YouTuberの動画のみに広告の掲載を指定することができます。
このプレースメントターゲットを行うことで、より高い広告効果が期待できると同時に、ブランド毀損のリスクを下げるブランドセーフティ対策としても有効です。
信頼できるメディア媒体のみに配信する

GoogleやYahoo!などのネットワークに広告を掲載するのではなく、広告を掲載したいメディアに直接、広告掲載の依頼をすることでブランドセーフティ対策になります。
例えば、有機野菜の配達をしているブランドの場合、オーガニックレシピを配信しているサイトやヴィーガン情報を配信しているメディアなどが対象になるでしょう。
ブランドイメージにぴったりのメディアがある場合、直接広告掲載の依頼をすることで、自社が把握していないサイトに掲載されることはなくなります。
広告代理店の配信先を自社内でも精査する
デジタル広告を掲載するときに、多くの企業が広告代理店を使いますが、自社でもブランド毀損のリスク管理をすることでブランドセーフティ対策となります。
実際に、ブランド毀損が生じたケースの多くは、ブランド主が意図していないことが多く、広告代理店のリスク管理の甘さや掲載先の規制が緩かったことが原因です。
そのため、広告代理店に任せっきりにするのではなく、自社内部でも広告の掲載先が適切であるか精査できる人材がいると安心です。しかし、広告代理店に任せることとダブルで人材を自社で設ける事になるため、人件費が発生するなどのデメリットがあります。
プライベートマーケットプレイスを利用する

プレイベートマーケットプレイスを利用することで、質の高い広告の掲載先に限定されるため、ブランドセーフティ対策になります。
「プライベートマーケットプレイス(PMP)」とは、広告を掲載する媒体と広告主(ブランド側)を限定したクローズドな広告取引市場のことを指します。
プレイベートエクスチェンジとも呼ばれていますが、高品質な媒体をプログラミングによって精査することができるため、ターゲティングを絞って広告を掲載可能です。ターゲティングを絞ることで、実質ブランドセーフティ対策につながる点がPMPのメリットと言えるでしょう。
各広告媒体で設定できるブランドセーフティ対策

ここでは、腫瘍媒体で実施できるブランドセーフティー対策を紹介します。
- Facebook・Instagram
- YouTube
- Yahoo
Facebook・Instagram
Facebook・Instagramでは、以下のブランドセーフティ対策が行われています。
- コミュニティ規定
- 収益化ポリシー
- ブランドセーフティコントロール

Twitterでは、以下のコンテンツに関して広告の制限がかけられていてブランドセーフティ対策が行われています。
- 性的な成人向け
- ヘイト表現や過激主義
- 攻撃的な発言
- 法的に禁止・規制されている商品・サービス
- センシティブ
- バイオレンス・刺激の強いもの
YouTube
YouTubeでは、以下のようなアプローチでブランドセーフティ対策が行われています。
- ホワイトリストとブラックリストの管理
- オープンスレートプラットフォームの利用(広告主が特定の動画をブロックできる機能)
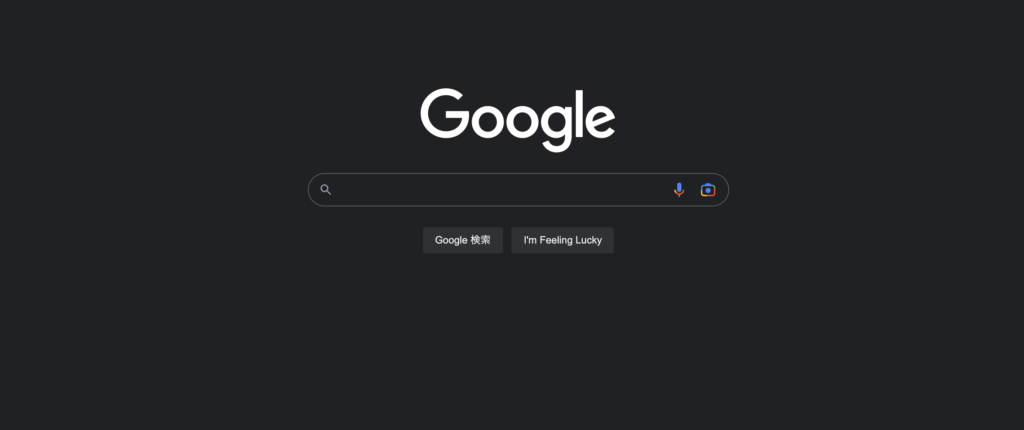
Googleでは、以下の審査を通じてブランドセーフティ対策が行われています。
- 強固な広告掲載ポリシー
- サイト運営者の管理設定
- 包括的な広告の管理
- ブランドイメージを継続的に保護するための管理
- 独自開発したアドなメージャーの高度な処理
Yahoo
Yahooでは、以下の審査を通じてブランドセーフティ対策が行われています。
- ビューアビリティ(視認性)
- アドフライド対策
- ブランドセーフティ
- プライバシーへの配慮
- 最適な広告フォーマット
- アドクラッター対策
アドベリフィケーションとは?

「アドベリフィケーション」とは、「Ad(広告)」と「Verification(要求に適したものか検証)」という意味の造語で、WEB広告の掲載先が適切か検証することを指します。
原則、WEB広告は、アクセス数の多いサイトであるほど広告費用が高く、アクセス数の少ないサイトであるほど広告費用が安くなります。価格設定は、広告主(ブランド側)が直接的に媒体に交渉した場合の話であり、ある程度のターゲティングをした上で、対象となるサイトに掲載されるのが基本です。
ターゲティングを細かくしすぎると、広告効果が伸び悩む場合もあるため、ターゲティングの細分化は難しいところですが、ゆるくしすぎると不適切なWEBサイトに掲載される可能性があるため、アドベリフィケーションが必要になります。
ブランドセーフティのために企業ができる対策とは?

ブランドセーフティのために企業ができる対策は以下のとおりです。
- 費用対効果を求めすぎない
- 自社内に広告部隊を構える
- 広告の効果を確認する
それぞれの対策について詳しく見ていきましょう。
費用対効果を求めすぎない
費用対効果の数値ばかりに着目してしまうと、不適切なサイトに掲載される可能性が高くなるため、広告効果を過剰に求めすぎないことが大切です。
費用対効果の高いサイトは、ワンクリックなどのミスリードを狙ったアダルトコンテンツや違法サイトなどが多いため、ブランドのイメージが下がってしまうものが多い傾向です。
そのため、費用対広告を最優先にすると不適切なサイトに掲載されやすくなるため、まずは不適切なサイトに掲載されることを避けることを最優先にしてください。
自社内に広告部隊を構える

お金を払って広告代理店を雇ったとしても、自社内で広告によるブランド毀損につながるリスクを管理する広告部隊を構えることでブランドセーフティに繋がります。
ただし、広告部隊を構えるということは、人材確保の必要が生まれて人件費が新たに発生したり、既存の人材を利用するのであれば仕事量が増える点でデメリットです。
広告代理店に任せっきりにして、ブランド毀損の被害にあった企業は、大手企業を含めて多く実例があるため、100%任せっきりにするのはリスクがあることを理解しておきましょう。
人件費がかかる点とブランド毀損のリスクがあることを把握した上で、自社内にブランド広告に関与する人材を確保すると安全性が一気に高まります。
広告の効果を確認する
常に広告の効果がどのように売り上げやブランド認知に影響しているかを確認するだけでもブランドセーフティ対策になります。
例えば、広告を出してからオンラインショップのアクセス数が伸びて、売り上げが上昇したのであれば、広告の効果が良い作用となっていると判断できます。一方で、広告を出してから売り上げが減少したり、SNSでの評判が下がったのであれば、広告が悪い影響を与えている可能性を考えましょう。
ブランド毀損の被害に遭った場合、少しでも早く対処することで炎上沈静化を図ることができるため、スピードが勝負になります。
ブランド広告が不適切なWEBサイトに掲載されていることが発覚した場合は、すぐに広告の掲載を止めてもらうための対処をとってください。
ブランドセーフティ対策を行うメリットとは?

ブランドセーフティ対策を行うメリットは以下のとおりです。
- ブランドイメージの毀損を抑制できる
- 広告効果を高めることができる
- 自社内でノウハウを貯めることができる
それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
ブランドイメージの毀損を抑制できる
ブランドセーフティ対策を徹底することで、広告によるブランドイメージの毀損を抑制することが可能になります。
ブランドイメージの毀損が拡散されてしまうと、サービスやモノの売り上げが著しく減少したり、不当な低評価をネット上で書き込まれたりしかねません。場合によっては、炎上の沈静化ができずに、店舗を閉店したり、ブランドのクローズにまで追い込まれるケースがあるため、深刻な問題です。
また、ブランドイメージの毀損は、ブランド側の意図していない部分で発生するケースも多いため、事前に対策を行うことが重要です。
事前に対策することで、ブランドイメージの毀損を抑制できたり、万が一ブランドイメージの依存の被害にあってもいち早く対処することができます。
広告効果を高めることができる

ブランドセーフティ対策を行うことで広告の効果を最大限発揮する事につながります。
ブランドセーフティ対策の一種である「ターゲティング」機能を有効に使うことで、広告が届くべき人に届けることが可能になるからです。
例えば、男性向けスーツのアパレルブランドが新たにデジタル広告を掲載することを検討している場合、ターゲティングを行わないと、女性や10代の学生たちにも広告が掲載されます。一方で、「ビジネスサイト」「男性ファッションサイト」などのターゲティングをすることで、スーツに興味がありそうなユーザーに対して直接広告を掲載することが可能です。
これによって、ブランド毀損に対するブランドセーフティ対策を行うだけでなく、広告効果を最大限に発揮する事になります。
自社内でノウハウを貯めることができる
デジタル広告の掲載を広告代理店に任せずに自社で行うことで、広告人材を確保したり、ブランドセーフティ対策に関する広告運用のノウハウを蓄積することが可能になります。
広告代理店に頼むことで、自社の人材を別の仕事に回すことができたり、広告運用にかかる人件費を削減することができる点でメリットです。
ただし、広告代理店に任せてもブランド毀損被害に遭う企業は多くあるため、初めから自社でノウハウを貯めながら、広告運用の専門的な知識を持った人材を確保すると安心です。
ブランドセーフティ対策について理解しよう
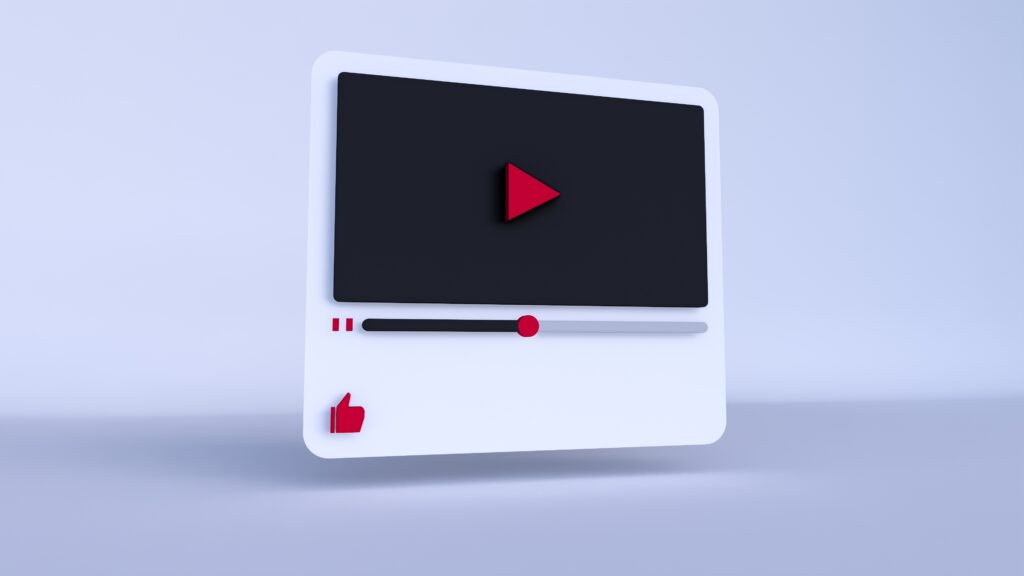
この記事の結論をまとめると、
- WEB広告によるブランド毀損を防ぐためには「ブランドセーフティ対策」を行う必要がある
- ブランドセーフティ対策とは、具体的に不特定のサイトへの掲載を許可せずに、手動で選択したり、プログラミングによって掲載サイトを精査することを指す
- ブランドセーフティ対策のほとんどは企業側で行える
- ブランドセーフティ対策を行うことで、ブランド毀損の被害を防ぐほかに、広告効果を高めたり、自社のノウハウを蓄積できるなどのメリットがある
ということがわかりました。
ブランドセーフティ対策は、WEB広告を掲載するブランド・企業が行うべき重要な管理のひとつです。
自社内で人材を確保したり、ノウハウを蓄えることが最適ですが、難しい場合は実績の多い広告代理店等を利用して、ブランド毀損のリスクを減らしましょう。



