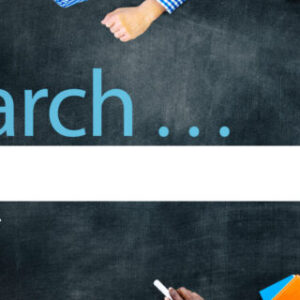誤爆とは? | 事例とともに防止策と起こった際の対処法まで徹底解説

インターネット上でしばしば話題に上がる誤爆について、あなたは知っていますか?
この記事では「誤爆とは」について解説していきます。結論、誤爆を防ぐには誤爆しないための体制作りが重要です。SNS導入を検討する際、知っておきたい「誤爆の防止方法」を調査した結果をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「誤爆」の説明や、「誤爆の良くある事例」「誤爆した時の対処法」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んでSNS運用に役立てていただければ幸いです。
また「ブログの炎上対策」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
誤爆とはネット用語の1つ

誤爆は、ネット用語の1つです。TwitterやLINEなどSNSにおいて、想定外の相手にメッセージを送ってしまうことを指します。別の言い方をすれば、送信ミスのことです。他にも以下の意味も含まれています。
- 予測変換によるミス
- 文字の打ち間違い
- 誤送信
スマートフォンの利用増加に伴い、多くの人がSNSに触れる時代になったからこそ起こる現象です。
元々は軍事用語
誤爆は元々、軍事用語です。誤って目的以外の場所を爆撃してしまうという意味を持っています。それが転じて、本来書き込む場所とは違う場所に書き込んでしまったという意味で使われるようになりました。
しかしながら誤爆によって炎上までしているケースを考えると、あながち遠くない言葉だとも言えます。
誤爆はSNS利用拡大によって発生したリスク

誤爆はTwitterやLINEなどのSNSを中心に起こっている現象です。古くは2chのような掲示板でも多く見られました。個人・企業問わず情報発信・共有をSNSで行っていると、どうしてもミスが生じてしまいます。人間なので仕方がありません。
スマートフォンによって簡単にアクセスし利用できるからこそ、ミスも起こりやすくなっています。うっかりミスからの誤爆を防ぐためにも、誤爆をしないための対策が求められています。
誤爆の良くある事例

誤爆には様々な原因がありますが、事例はほとんど似通っています。SNSのシステムを通じて発生する物だからです。この項目では過去にあった誤爆の事例を以下にわけて解説します。
- Twitterでの誤爆
- LINEでの誤爆
- 有名人の誤爆
Twitterでの誤爆
Twitterでの誤爆は非常に多いケースです。気軽に情報を発信でき、かつ拡散もしやすいことから誤爆の起こりやすい環境が整っています。過去には以下の事例が確認されています。
- 企業の公式アカウントが仕事の愚痴をツイート
- アニメの公式アカウントが別のアニメのツイートをしてしまった
- アカウント管理者の子どもが、スマートフォンを使って全く関係のない内容のツイートをしてしまった
このように、誤爆のほとんどがTwitterアカウントを複数持っていることで起こっています。良くあるのが、裏アカウントやサブアカウントだと思っていたら本アカウントだったというパターン。
ツイート前の確認を怠ることで起こる誤爆と言えます。
LINEでの誤爆
LINEでの誤爆もTwitterと並んで多くあります。しかしLINEの場合、個人的な誤爆がほとんどとなっています。以下がその代表例です。
- パートナーに送るメッセージを親に送ってしまった
- 友達に送るメッセージを上司に送ってしまった
- 告白相手を間違えた
このような誤爆が多いため、特殊な場合を除いて謝れば何とかなる場合がほとんどとなっています。個人と企業向けサービスが切り分けられているのも、影響としては大きいでしょう。
ユーザー間の個人的な誤爆が中心となっています。
有名人の誤爆

有名人の誤爆も非常に多くあります。主に見られるのは、やはりTwitterです。過去には以下のような事例が起こりました。
- ロンドンブーツ1号2号の田村亮さんが、芸人の謝罪会見を見て「ひどい記者」とツイートして炎上
- 俳優の伊勢谷友介さんがSMAP解散に対するマスコミに対して「どうでもいいこと」とツイートして炎上
- 指原莉乃さんが著書の宣伝のために裏アカウントでファンを装ってツイートをして炎上
このように有名人でも様々な誤爆があります。人である以上、どれだけ気をつけていても誤爆のリスクは付きまとうものです。誰でも起こりうることだと認識しておきましょう。
誤爆してしまったときの対応

もし誤爆をしてしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。誤爆はどれだけ気をつけていても、起こるときは起こります。大切なのは、誤爆した後にどのように対応したかです。
企業でSNSを活用する際は、運用開始と同時に誤爆への対応を決めておくと良いでしょう。特に以下は重要な対応です。
- すぐに削除する
- すぐに謝罪する
- 再発防止策を発信する
すぐに削除する
誤爆をしたとわかったら、まず誤爆した内容をすぐに削除してください。誤爆したものをそのまま放置しておくと、余計に広がってしまうのがインターネットだからです。時間を置くと手が付けられなくなることも。
魚拓といって誤爆した内容をスクリーンショットで保存する人も多くいるため、なるべく早く手を打つことが大切です。
誤爆の際は、まず迅速に削除しましょう。
すぐに謝罪する
誤爆した内容を削除したら、すぐに謝罪します。時間を空けると心証が悪くなるからです。迅速な対応を心がけましょう。
この際に気をつけたいのが、謝罪がお粗末にならないこと。良くある謝罪として、乗っ取りの被害に遭ったというものがあります。近年、政治家を含めた多くの人が使っている謝罪方法です。しかしこれは悪手中の悪手。アカウントが乗っ取られるということは、セキュリティ管理が甘いという裏付けでもあります。余計に責められるでしょう。
謝罪には誠実さが何よりも大切です。誠実に対応することでプラスのイメージがつくこともあるため、内容を吟味した上で発信してください。
再発防止策を発信する

削除と謝罪が済んだ後、次は再発防止策を発信します。そうすることで、誤爆に対して真摯に向き合っている姿勢を示せるからです。
再発防止策は以下の内容を組み込むと良いでしょう。
- 誤爆が起こった原因
- 原因から考えられる再発防止策
この2つは必ず盛り込んでください。また、迷惑をかけた相手に謝罪を発信することも大切です。裏で直接謝罪していたとしても、第三者からは見えません。誤爆した場所でしっかり謝罪を発信することで印象も良くなります。
ここまで対応して、ようやく誤爆の対応は一段落します。
誤爆の防止方法

誤爆は基本的に人為的ミスで起こります。システム上で誤爆することはありません。そのため、誤爆をしないためにも投稿前に確認する体制を整える必要があります。中でもオススメの方法は以下の6つです。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ダブルチェックを行う | 誤爆の確率が下げる ファクトチェックも可能 | スピード感がなくなる |
| 内容を考える人と投稿する人をわける | 誤字脱字のチェックができる ファクトチェックも可能 | スピード感がなくなる |
| アカウントごとにアプリをわける | アカウントの誤爆がなくなる | 複数のアプリを使い分ける手間が発生する |
| 特定のアプリをロックするアプリを導入する | 第三者からの操作を防げる | アプリによっては乗っ取りの可能性がある |
| 個人用と業務用の端末を物理的にわける | 端末をわけているので誤爆の確率が下がる | 物理的に荷物になる |
| HPとアカウントを連携させない | 情報の精査を行った上で発信できる | 連携時よりも作業工程が増える |
それぞれ詳しく解説します。
ダブルチェックを行う
ダブルチェックを行うことで誤爆に対して有効的です。チェックの目を増やすことで、うっかりミスを大幅に防ぐことができるでしょう。Twitterの場合、以下の項目をダブルチェックするのがオススメです。
- 投稿の内容
- 投稿時間
- 発信するアカウント
これらを確認することで、誤爆の確率が大きく下がります。特に社内から投稿する場合において、大きな効果を発揮してくれます。
一方でダブルチェックによってスピード感は大きく削がれます。迅速に情報を発信したい場合には注意が必要です。
内容を考える人と投稿する人をわける
内容と考える人と投稿する人をわけるのも効果的です。社内で勤務時間のみ仕事として情報発信している場合に有効的でしょう。内容を考える人とわけることで、誤字脱字やファクトチェックも同時にできます。
初歩的な誤爆を防ぐ面において、大きな効果を発揮するでしょう。
一方で運用が二人三脚となるため、スピード感はどうしても落ちてしまいます。
アカウントごとにアプリをわける

アカウントごとにアプリをわける方法も誤爆防止に効果的です。特に運用担当者が1人の場合に効果を発揮してくれます。このアカウントならこの情報、というようにわかりやすいので誤爆が減るのです。
複数アプリを管理できるアプリだと、簡単な反面、アカウントの誤爆が起こりやすいのが難点となっています。そのため手間ではありますが、1アカウント1アプリで使い分けます。Twitterの場合、以下のようになるでしょう。
- Aアカウント:Twitter公式アプリから
- Bアカウント:TweetDeckから
- Cアカウント:SocialDogから
このようにアプリをわけることで、アカウント発信時の誤爆を極力防ぐことができます。一方でアプリの数が多くなるため、管理の手間はどうしても増えてしまうので注意してください。
特定のアプリをロックするアプリを導入する
特定のアプリをロックするアプリを導入するのも誤爆を防ぐ上で有効です。業務で使用するアプリにロックをかけることで、使用前に誤爆に気付く仕組みを作ります。
スマートフォンの起動にロックをかけるのと同じ考え方です。
ロックをすることで、誤爆以外にも第三者からの操作や、子どもの悪戯からもアカウントを守れます。業務用の端末を社外に持ち出している方には効果的な誤爆防止方法です。
一方でアプリをロックするアプリは慎重に選ぶ必要があります。最悪の場合、アカウント乗っ取りになる可能性もあるため注意しましょう。
個人用と業務用の端末を物理的にわける
個人用と業務用の端末を物理的にわけるのも有効です。業務用の端末でのみ発信するように決めておけば、誤爆を起こす可能性が大きく下がります。アカウントではなく端末そのもので使い分ける考え方です。
この場合、デメリットとして複数台持ち歩くと費用と手間がかかります。業務用なので、会社から支給してもらえるのであればそれを使うのがオススメです。
ただし注意点として、常に持ち歩くのであれば端末本体のセキュリティ対策が必須となります。持ち歩く端末が増える分、セキュリティ面も含めて負担が増えることは覚えておきましょう。
HPとアカウントを連携させない

HPとアカウントを連携させないことも誤爆対策の1つです。アカウントを連携していると、間違って連携している別のアカウントで発信してしまう可能性があります。それを防ぐために、あえて連携しないのです。
アカウント連携は非常に便利な機能となっています。反面、情報発信において精査しないと誤爆する可能性が多いにあります。これは大きなデメリットです。
手間にはなりますが、アカウントを連携させないことで発信前に1度確認する時間を作れます。
誤爆を防止するためにも、連携させているアカウントは一度精査してみましょう。
誤爆は予防と対応が大切

SNSが発達した現代において、誤爆は常に起こりうるリスクです。個人・企業問わず誰しも起こしてしまうものだと考えた方が良いでしょう。過去には有名人が誤爆によって炎上したケースも多々あるほどです。
もし誤爆をしてしまった場合は、すぐに削除し謝罪するようにしましょう。迅速に対応することによって余計な拡散を防げます。同時に再発防止策を検討・発信することで、誠実さもアピールできます。ぜひ実践してください。
ただ誤爆はしないに越したことはありません。誤爆を防止するにはダブルチェックや端末を使いわけるなど様々な方法があります。自社の運用方法にとってどの方法が良いのかを検討した上で、誤爆防止策を導入してくださいね。