風評被害の実例とは?影響や発生する原因も詳しく紹介

風評被害について詳しく知っていますか?
この記事では「風評被害の実例」について解説していきます。結論、風評被害は実例をもとに何が原因になりうるのかを具体的にイメージすることが重要です。
風評被害を検討する際、わかりづらい「風評被害の実例」を調査した結果をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「風評被害」の説明や、「風評被害の影響」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んで風評被害について知っていただければ幸いです。
また「ブランディング」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
風評被害とは?

「風評被害」は、真実とは異なる情報や意図的に悪意のある情報発信を行なったことで、「経済的な損害」を被った時のことを指す言葉です。
一般的に、フェイクニュースやデマを通して悪いイメージが浸透することを指す言葉として認識されていますが、「経済的損害」が加わることで風評被害を受けたことになります。実際にトラブルを起こしたことが原因で経済的な低迷をした場合、「過失」が原因ですので、風評被害に遭ったとは言いません。
風評被害のケースとして、第三者が悪意を持って根拠のない噂やデマを拡散することもありますが、事件や事故が起きた後、メディア報道やネットの口コミで無関係の企業・個人が悪い印象を植え付けられてしまうこともあります。
後者の場合、発信者に悪意がなくても、対象となる企業・個人は、風評被害によって経済的損害を受けるため、巻き込まれないような対策が必要です。
風評被害の実例

風評被害の実例は次のとおりです。
- 株式会社コロナの名称の事例
- 原子力発電所事故における福島県産野菜の実例
- 佐賀銀行の倒産デマの事例
- ドミノピザアルバイトの事例
- 船橋屋の同名小企業の実例
- アサリ産地偽装問題に関連したはまぐりの事例
- 日本大学アメリカンフットボール部の事件に関連した日本体育大学の事例
- 口蹄疫の流行における宮崎県の事例
- ウェンディーズのデマ情報の事例
それぞれの実例について詳しく解説します。
株式会社コロナの名称の事例

新型コロナウイルスの蔓延により、新潟県三条市にある株式会社コロナが会社名が流行病と同じであることを理由に風評被害を受けました。
株式会社コロナは、昭和10年に商標登録をして、創業昭和12年と長い歴史のある企業で、現在は東証一部上場しています。しかし、コロナウイルスが猛威を振るい、公式サイトに悪質な書き込みが多少散見されるようになったり、周りから名前のことを心配される反応を受けたと話します。
こういった事態に対して、株式会社コロナは、一貫して反応をしない・反論をしないことに徹した上で、株式会社コロナの社名の由来に関する広告を出した結果、大きな反響を集めました。
多くのメディアからの取材もあり、新潟県内からの支持率も高くなり、社員の士気も高まる良い方向へと舵を切ることができました。
一方で、コロナビールや大阪にあるコロナホテルなど、「コロナ」という名前がついているだけで、人々から敬遠されて売り上げに影響した企業も多いようです。
原子力発電所事故における福島県産野菜の事例

東日本大震災による原子力発電所事故で、放射能汚染されたと大きく報道されたことを理由に福島県産野菜が風評被害に遭いました。
東日本大震災で大きな津波が福島県を襲った結果、原子力発電所から大量の放射能が放出される大惨事へと発展。世界的にも大々的に放射能の恐ろしさが報じられた結果、10年以上経っても「福島県産の食べ物は汚染されている」というイメージが消費者の間に植え付けられてしまいました。
日本のスーパーなどで流通する食品は、日本が定める安全基準をクリアしたもののみですので、店頭に並んでいるということは安全性が確保されている証です。
それでも、過去の報道が根強く消費者の記憶に残り続けていることでいまだに「福島県産である」という理由で手に取られないという現状があります。
佐賀銀行の倒産デマの事例

2003年、「佐賀銀行が潰れるそうです」といった内容のチェーンメールが拡散されたことによって、佐賀銀行が風評被害に遭いました。
チェーンメールは、瞬く間に拡散され、一夜にして窓口とATMは多くの人が押しかけ総額450億円〜500億円の預金が引き出され、通常の2倍の人が押しかけたことが分かっています。
利用者の中には、預金を引き出すだけではなく口座の解約手続きまで行っていたということで、大混乱となりました。
ドミノピザのアルバイトの事例

ドミノピザのアルバイト店員がシェイクをヘラで救って舐める動画を投稿したことで、ネットで大炎上し、風評被害に遭いました。
投稿された動画は、全国にあるドミノピザのある店舗で行われたのですが、どの店舗で行われたかが発覚するまで他の店舗にも客足が遠のいてしまったのです。
店舗の運営形態に関しては、直営店やフランチャイズ店などさまざまですが、1箇所の店舗のアルバイト教育が徹底されていなかったことが原因で他の店舗に悪影響が及んだことは理解しておくといいでしょう。。
船橋屋の同名称企業の事例

元祖葛餅として知られる「船橋屋」の社長・渡辺雅司が交通事故を起こした際に相手側に暴言を吐いていた動画が拡散された件で、同名称企業が風評被害に遭いました。
渡辺雅司は、原因がほとんど自分にあるにも関わらず、交通事故の被害者側の車に詰め寄り恫喝する様子がドライブレコーダーに記録されていて、Twitterで拡散されます。結果、船橋屋の社長を解任させられて、相手側と示談することで話は落ち着きました。
しかし、世間には「船橋屋」という名前の同名称の企業があり、今回の事件とは関係ないにも関わらず、多くのクレームが寄せられる事態に発展しました。
元祖葛餅「船橋屋」は、無関係の企業への問い合わせを控えるように要請を出しましたが、事態を収集するのに時間がかかったようです。
アサリ産地偽装問題に関連したはまぐりの事例

熊本県産のアサリに産地偽装の疑いが判明したことで、他のアサリやハマグリなどの貝類が風評被害に遭いました。
2022年2月、農林水産省の調査により、「熊本県産」と表示されていたアサリの97%が「外国産アサリ混入の疑いあり」と判明したのです。
食品表示法では、輸入したアサリは、育てた場所が長い方を「産地」として表示する義務がありますが、そのほとんどが熊本県より中国での期間が長いにも関わらず、「熊本県産」と偽装されてました。結果的に、消費者からの信頼を失くし、ハマグリ等の関係ない食品まで消費量が減ってしまいました。
日本大学アメリカンフットボール部の事件に関連した日本体育大学の事例

日本大学アメリカンフットボール部が悪質なタックルプレイをして、相手チームの選手を負傷させた問題で、名前のにた「日本体育大学」が風評被害に遭いました。
当時、社会問題として大きな議論を巻き起こした悪質タックル事件ですが、日本大学だけでなく、名前が似ている日本体育大学と勘違いする人が続出。
スポーツのイメージもあることから、誤解されてしまったようなのですが、名前による風評被害は頻繁に発生していることが伺えます。
口蹄疫の流行における宮崎県の事例

牛や豚などの家畜動物の間で広がる「口蹄疫」が宮崎県で大流行してしまい、長年宮崎県産の食品が風評被害に遭うことになりました。
口蹄疫は、動物の伝染病の一種であり、感染した家畜の30万頭が殺処分の対象となり大きな注目を集めることになりました。
多くのメディアは口蹄疫の危険性などを大々的に報道したことにより、口蹄疫に感染した家畜を食べても人体に影響がないという根拠があるにも関わらず、人々の間で悪いイメージが浸透します。結果的に、「宮崎県産の肉は危険」という認識で売り上げが落ちてしまったのです。
ウェンディーズのデマ情報の事例

ウェンディーズが発売した「台湾メロンパン」が実際の台湾の食文化に存在しないものとして炎上し、風評被害を受けました。
ファストフードチェーン店のウェンディーズの一部の店舗では、台湾や香港で親しまれている台湾メロンパンの新商品を発表します。しかし、実際には「台湾メロンパン」ではなく「香港パイナップルパン」であるとのこと。
台湾と香港では異なる食文化が存在することから、他文化へのリスペクトが欠けるとしてイメージが悪くなりました。
風評被害がもたらす影響とは?

風評被害がもたらす影響は次のとおりです。
- 取引先からの信用の低下
- 株価の低下
- 自社製品ブランドの評判低下
それぞれの影響について解説します。
取引先からの信用の低下
風評被害に巻き込まれると、取引先からの信用が下がってしまい今後の取引に悪影響を及ぼす可能性があります。
取引先との関係は、「利害性」が重視されるため、風評被害で売り上げが落ちたり、社会的なイメージが下がってしまうと、取引先は価値がないと判断しかねません。取引先との関係が崩れてしまうと、結果的に自社のビジネスの経営が傾くことになります。
風評被害に巻き込まれたのであれば、事実無根であること、どう対処するかを明確にして信頼関係を崩さずにいることが大切です。
株価の低下

風評被害に巻き込まれると、株主達からの信用度が下がってしまい、今度の株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
株価は、買い手と売り手のバランスによって決定するため、経済的な期待や企業・ブランドへの期待が高いほど株価は上がる仕組みです。
つまり、風評被害によって、企業への期待が下がったり、ブランド価値がないと判断されると、売り手が増加し、株価が下がってしまうのです。
風評被害にあった際、しっかりと対処して企業存続の力を持っていることを証明したり、消費者たちからのイメージ回復を行うことができれば、株価が下がる心配は少ないでしょう。
自社製品ブランドの評判低下
風評被害に巻き込まれると、消費者たちからのイメージが下がってしまい、ブランド価値・評判に悪影響を及ぼす可能性があります。
特にネット上などで炎上してしまった場合、拡散された情報を見たネットユーザー全てを訂正することはできません。ネット炎上の規模が大きいほど、収集がつかなくなってしまう傾向にあります。
結果的に、真偽を問わず、消費者たちからのイメージダウンにつながり、ブランド価値が下がったり、評判が悪くなってしまう可能性が高いです。
企業がすべき風評被害対策とは?

企業がすべき風評被害対策は次のとおりです。
- 自社社員へのコンプライアンス研修の実施
- 逆SEO業者への依頼
- 速やかな状況報告と謝罪文の掲載
それぞれの風評被害対策について詳しく解説します。
自社社員へのコンプライアンス研修の実施
自社社員へのコンプライアンス研修を丁寧に行うことで、社員・パート・アルバイト全ての人が意識を高く持って仕事に取り組み、風評被害のリスクを減らすことができます。
例えば、バイトテロのような事件は、仕事をすることの責任や意識が低い10代が起こしがちです。
「仕事をするとはどういうことなのか」「バイトテロを起こすとどのような責任が生じるのか」を教育することで、従業員全体の意識改革につながります。
逆SEO業者への依頼

インターネット上で、企業や個人の悪い情報が出回っていて「企業名 ブラック」「企業名 詐欺」などのネガティブワードが表示されると風評被害に遭いやすくなります。
そこで、逆SEO対策業者に依頼をすることで、ネガティブワードをポジティブワードに変換するサービスを提供してもらえます。
企業や個人について検索をしたネットユーザーがネガティブなワードではなく、ポジティブなワードを目にすれば、風評被害のリスクを最小限にまで抑えることが可能です。
速やかな状況報告と謝罪文の掲載
万が一、炎上などに巻き込まれた場合、素早く状況を把握した上で、事実と謝罪を公開することで沈静化をはかり、風評被害の規模を最小限に抑えることができます。
対応が遅れるほど、ネット炎上は拡大するため、ネットのトラブルはスピード勝負であることを理解してください。
インターネット上で、何が起こっていて、何が批判されているのかを的確に把握した上で、正しい謝罪文を掲載することが求められます。
風評被害が発生する原因とは?
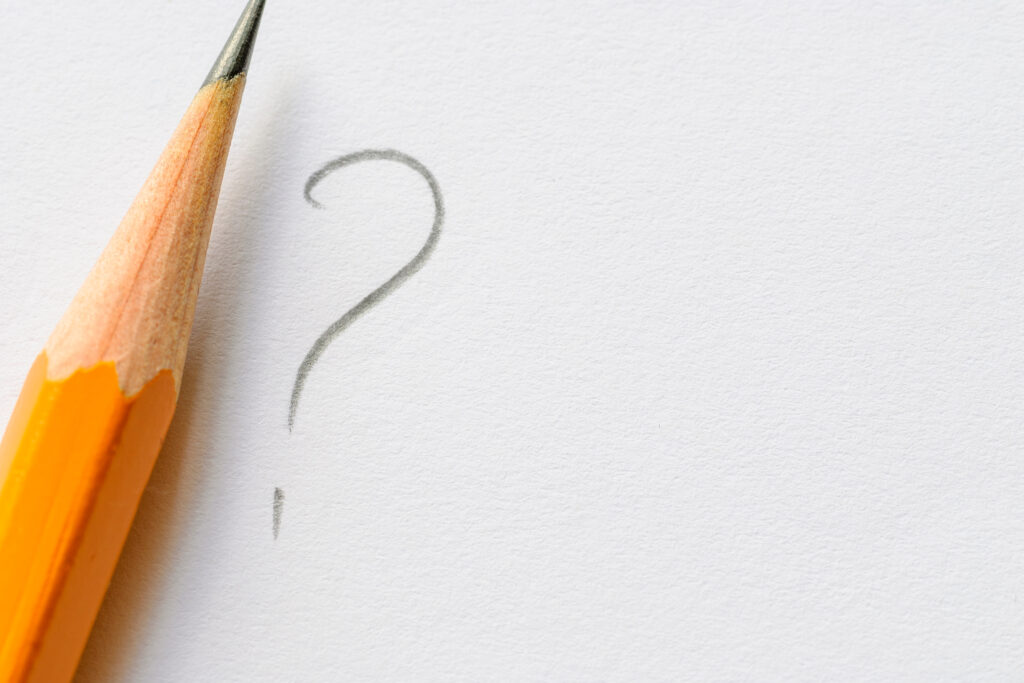
風評被害が発生する原因は次のとおりです。
- SNSなどでのデマ情報の拡散
- 自社社員・商品に関連する不祥事
- メディアの偏向報道
それぞれの原因について詳しく解説します。
SNSなどでのデマ情報の拡散
風評被害の原因としてSNS等のデマ情報の拡散があります。
基本的に自由な発言が許されているSNSですが、捨て垢など個人が特定できないアカウントから事実と異なる情報やデマが拡散されて、風評被害を受ける事例が多発しています。
事実ではない場合、拡散元のアカウントに削除依頼をしたり、公式サイトで事実ではないことを発信したり、場合によっては開示請求などで対処してください。
自社社員・商品に関連する不祥事

風評被害の原因として内部で発生した不祥事があります。
バイトテロなどの従業員のミスや、商品の欠陥などがあると、関係のない店舗も売り上げに影響したり、企業全体のイメージが下がってしまうためリスク管理が必要です。
従業員教育を徹底したり、商品管理を見直すなどして、自社内部からトラブルが発生しないような対策をしてください。
メディアの偏向報道
風評被害の原因としてメディア報道があります。
メディアで発信されたことが間違った認識を与えてしまうと、原子力発電事故の福島県産食材や口蹄疫の宮崎県産食材のような風評被害を受けかねません。
特にメディアの影響は、数年・数十年後にも根強く残りがちのため正しい情報を訂正して発信するなどの対処をしてください。
風評被害の実例を理解しよう

この記事の結論をまとめると、
- 風評被害は、フェイクニュース・デマの拡散だけではなく「経済的損害」を受けた際に使われる言葉である
- インターネットの普及とともに風評被害の数と規模は増え続けているのが現状
- 全く関係のないところで発生した事件や事故によって風評被害に巻き込まれるケースもある
- 風評被害を受けた際は、正しい情報を素早く発信することが求められる
ということが分かりました。
インターネットがあり続ける限り、風評被害がなくなることはありませんので、ビジネスをする上で、風評被害に巻き込まれないための工夫・対処法を用意しておくことが大切です。
たとえ、企業側に非がない場合でも、ブランドイメージが落ちたり、売り上げに悪影響を及ぼすリスクがあるため、全ての企業が懸念すべき問題です。



