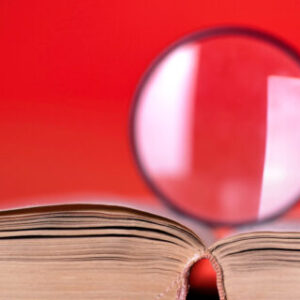インターネットホットラインセンターの効果とは?役割や目的も詳しく紹介

インターネットホットラインセンターが設置されたことでの効果を理解していますか?
この記事では「インターネットホットラインセンターの効果」について解説していきます。結論、インターネットホットラインセンターが設置されたことでインターネット上の違法情報の通報窓口として機能することになりました。
インターネットでの通報を検討する際、わかりづらい「インターネットホットラインセンターの効果」を調査した結果をまとめたので、ぜひ見ていただければと思います。
その他にも「インターネットホットラインセンター」の説明や、「インターネットでの問題」について説明していきたいと思いますので、ぜひこの記事を読んでインターネットホットラインセンターの効果について知っていただければ幸いです。
また「ブランディング」について知りたい方は、こちらで解説を行っていますのでぜひ確認してみてくださいね。
インターネットホットラインセンターとは?

インターネットホットラインセンターとは、インターネット環境を健全に保つため、「違法性」「有害性」のある情報に対処する目的で作られたサイトです。
具体的には以下の5つの項目に当てはまる場合、インターネットホットラインセンターへの通報が推奨されます。
| わいせつ・アダルト | 明らかに性器が確認できる無修正画像やそれに近い画像が掲載されている場合(学術・医学・芸術目的を除く) |
| 児童ポルノ | 児童(18歳未満で実在する人物)との性交・性交に近しい行為・裸・一部の衣類を脱いでいる画像が掲載されている場合 |
| 薬物・ドラッグ | 違法薬物の使用を煽ったり促すこと、販売目的の書き込み・広告が掲載されている場合 |
| 出会い系・売春 | 金銭が絡んだ性行為の募集、出会い系サイトで18歳未満の児童に向けた性交・援助交際の募集、児童側からのアプローチが掲載されている場合 |
| その他 | 自殺の誘引、振り込め詐欺、フィッシング、他人の個人情報を晒す行為が掲載されている場合 |
インターネットホットラインセンターの実績とは?

インターネットホットラインセンターの公式サイトによると、令和3年1月から12月までの1年間で、405,572件の通報数が受理されています。
405,572件の通報数のうち、運用ガイドラインに基づき分析した件数は、405,702件に上ります。さらに、分析結果から違法情報と判断されたものが41,944件あったことが報告されました。
また、違法情報に続いて、自殺誘引等の情報も多く出回っていると報告されました。
インターネットホットラインセンターの役割とは?

インターネットホットラインセンターの役割は次のとおりです。
- 警察への情報提供
- プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼
- 関係機関等への情報提供等
- 国際連携による違法情報の処理
それぞれの役割について詳しく解説します。
警察への情報提供
インターネットホットラインセンターは、インターネット上の情報で刑罰法規に違反する疑いがあった場合は、すぐに警察へ情報提供を行っています。
具体的には、次のような情報が対象になります。
- 特定の犯罪に関する情報(法禁制品の販売など)
- 犯罪関連情報
- 自殺関連情報
- 犯罪捜査
- 犯罪予防
- 人命保護
実際にインターネットホットラインセンターに報告された情報には、違法と判断されたものも多くあるのが現状です。
プロバイダや電子掲示板の管理者等に対する対応依頼

違法情報が報告された場合、一定の範囲の情報については、プロバイダや電子掲示板の管理者に対して、「送信防止措置」などの対応を依頼します。
プロバイダや電子掲示板の管理者に、送信防止措置を依頼することで、悪質な書き込みがされても他社の目に届かなくなります。
関係機関等への情報提供等
報告された情報の内容によっては、専門的な対応・措置をとってくれる関係機関・団体に情報を提供しています。
国際連携による違法情報の処理
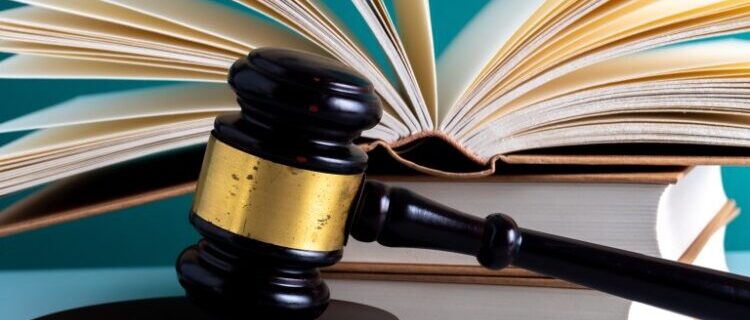
インターネットホットラインセンターは、INHOPE(ホットラインの連合組織)と連携をとっているため、必要に応じて国境を超えた違法情報の交換を行います。
インターネット上には、毎日膨大な数の情報が新たに掲載されていることに加えて、海外に設置されたサーバーを利用すると、違法な情報を発信する元が特定できないケースがあります。ただし、悪質性の高いもの、違法性があると判断されたものの場合、海外のホットライン連合組織と連携を取ることになり、今までは特定できなかった個人を炙り出すことが可能です。
現時点で、インターネットホットラインの国際連合組織に加入している国は、日本以外にイギリス・アメリカ・オランダ・フランス・ドイツ・オーストラリア・アイルランドなどがあります。
インターネットホットラインセンターに通報することで効果が見込める情報とは?

インターネットホットラインセンターに通報することで効果が見込める情報とは、次のとおりです。
- 違法情報
- 公序良俗に反する情報
- 違法情報と疑いが相当程度認められる情報
- 人を自殺に勧誘・誘引する情報
それぞれの情報について詳しく解説します。
違法情報
インターネット上に違法情報が掲載されていた場合、インターネットホットラインに通報することで、犯罪者の逮捕につながります。
具体的には次のような情報が掲載されていると違法情報と判断して良いです。
- 児童ポルノ画像
- わいせつ画像
- 覚醒剤等規制薬物の販売に関する情報
- 口座売買の勧誘・誘引
- インターネット上に掲載することが違法となる情報の掲載・ウェブサイトの管理
このような情報がインターネット上に掲載されていた場合、インターネットホットラインセンターに通報することで、警察へ情報提供してもらうことができます。
公序良俗に反する情報
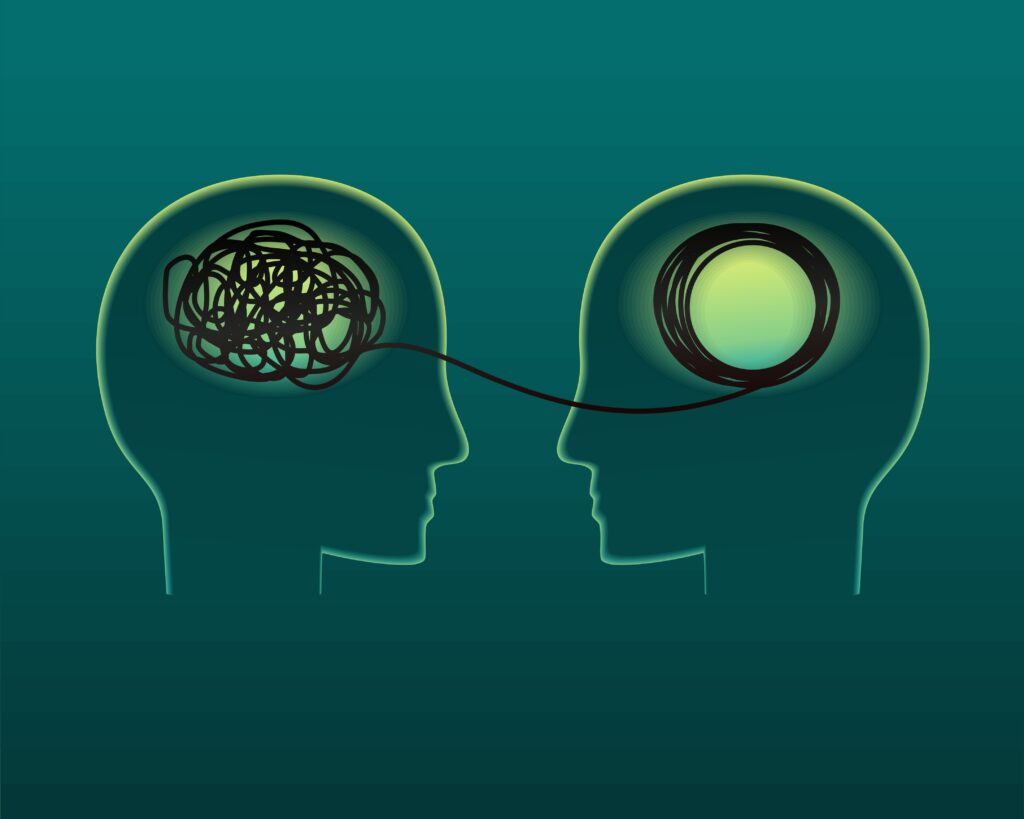
違法でない場合でも、その情報が社会的妥当性を持たないのであれば、インターネットホットラインに通報することで、掲載の取り消しにつながります。
誹謗中傷や差別発言などは、現時点で具体的な法律で罰則が定められていませんが、不適切な発言で誰かが傷つくのであれば、公序良俗に反します。
また、インターネット上でフェイクニュースを発信したり、冗談半分でデマ情報を拡散することも公序良俗に反すると判断されるケースがあるため気をつけてください
違法情報との疑いが相当程度認められる情報
違法情報を執拗に掲載する投稿やウェブサイトをインターネットホットラインに通報することで、アカウントの停止やサイトの閉鎖につながります。
確実でなくても、詐欺っぽいという場合でも、インターネットホットラインに通報することで、判断してもらうことができるため、怪しい段階でも通報して問題ありません。
人を自殺に勧誘・誘引する情報

自殺を勧誘する内容・誘引する投稿があった場合、インターネットホットラインに通報することで、掲載内容を非公開にすることができたりします。
自殺関連の情報は「有害情報」として判断することもできるため素早く対処されやすいです。実際に、硫化水素ガスを用いた集団自殺を行った場合、使用する量によっては近隣住民等にまで被害が拡大する事案が発生したことがあるからです。
警察庁は、インターネット上で硫化水素ガスの製造を誘引する投稿・ウェブサイトなどの募集があった際は、すぐにプロバイダ等の削除措置を依頼するようインターネットホットラインセンターに指示しています。
インターネットホットラインセンターが設置された効果とは?

インターネットホットラインセンターが設置された効果は次のとおりです。
- インターネット上の違法情報の通報窓口の明確化と一本化
- 日本国外との連携の強化
- インターネット犯罪の抑制効果
それぞれの効果について詳しく解説します。
インターネット上の違法情報の通報窓口の明確化と一本化
今までは、インターネットに掲載されている違法情報をネットユーザーが見かけても警察に連絡をする以外の手段がありませんでした。
しかし、警察はインターネットの違法情報措置以外にも一般的な事件や書類手続き変更などの業務があるため、多くの時間を割くことはできません。そこで、インターネットホットラインセンターが設置されることで、まずはインターネット情報の違法性・悪質性を判断して必要に応じて警察に情報提供する流れができました。
インターネット上の情報流通に特化した対応機関を設けることで、確実に悪質なユーザーを特定したり、より監視の目を光らせることができるようになっています。
日本国外との連携の強化

インターネットホットラインセンターは、日本国内だけで行われている機関ではなく、世界規模の機関が提携しているため、より犯罪行為の炙り出しが簡易化されています。
従来であれば、日本国内にいても海外のプロバイダを使うことで足跡を残さずに違法行為・悪質行為を行うことができました。
しかし、インターネットホットラインが世界各国で提携して繋がりを強化したことで、国境を超えたやりとりにも取り締まりができるようになったのが現状です。
インターネット犯罪の抑止効果
インターネットホットラインセンターによって、インターネット利用者が気軽に悪質なユーザーや違法性のあるウェブサイトを告発できるようになりました。
告発できるようになったことで、サイトが閉鎖に追い込まれたり、プロバイダから直接公開規制がかけられたりなどの措置が行われています。
多くの措置が行われていることによって、既存の犯罪性の高い投稿・ウェブサイトが取り締まられているため、インターネット犯罪がやりにくい環境を作っています。
インターネット上の課題・問題とは?

インターネット上の課題・問題は次のとおりです。
- 著作権違法の海賊版コンテンツの流布
- 第三者を侮辱する発言
- 個人間取引における金銭トラブル
- 個人情報の流出
- 不適切情報の拡散によるブランド毀損
それぞれの課題・問題について詳しく解説します。
著作権違反の海賊版コンテンツの流布
インターネット上の課題・問題として、著作権違反の海賊版コンテンツが多く流通していることが挙げられます。
海賊版コンテンツといえば、漫画・動画などが一般的に知られています。実際に、出版広報センターの情報によると、漫画の海賊版コンテンツの流布による国内の損害額は500億円と報告されました。
海賊版漫画サイト「漫画村」が開設されてから閉鎖されるまでの期間の損害額は3,200億円になるとのことで、いかに海賊版コンテンツによる被害が大きいかが伺えます。
第三者を侮辱する発言

インターネット上の課題・問題として、第三者を侮辱する「誹謗中傷」が多く投稿されていることが挙げられます。
誹謗中傷は、時に人の命を奪うだけの力を持っているため、これから法律面でも厳しい規制が設けられること間違いなしです。
個人間取引における金銭的トラブル
インターネット上の課題・問題として、個人間取引における詐欺等の金銭トラブル問題が挙げられます。
ネットワークビジネスや副業などで高額報酬が得られるとの文言で、初期費用を徴収するなどさまざまな詐欺まがいな行為が発覚しています。
個人情報の流出

インターネット上の課題・問題として、個人情報の流出による被害が挙げられます。
メールアドレス・住所・名前・パスワードはもちろん、プライバシーに関する個人情報が一度流出されると、完全にネット上から削除することはできません。
ネット上で削除されても一度拡散された情報は、個人が保有することもできるため、被害を減らすためには規制が必要です。
不適切情報の拡散によるブランド毀損
インターネット上の課題・問題として、不適切情報の拡散によるブランド毀損のリスクがあることが挙げられます。
ブランド毀損とは、広告の掲載先やブランドに関するフェイクニュース・デマなどが拡散されて、ネットユーザーのブランドに対するイメージが落ちることを指します。
多くのネットユーザーは、ひとつの情報に対して細かい真偽を確認しないため、フェイクニュースやデマなども簡単に拡散されてしまう点が問題です。炎上の規模によっては、売り上げが下がったり、ビジネス撤退まで追い込まれる可能性があるため、ビジネスをする上では警戒が必要です。
インターネットホットラインセンターが無能と言われる理由とは?

インターネットホットラインセンターは、多くのネットに関する通報を受けており、対応の順番待ちがあるため、「無能」と言われてしまうことがあります。
実際に、冤罪情報と殺害予告を受けたネットユーザーがインターネットホットラインセンターに連絡をしたところ、4日経っても返答が得られなかったと話しています。脅迫等の文章が直接送られてきたのであれば、誰もが不安になるかもしれません。
インターネットホットラインセンターの公式サイトでは、以下の2点が注意事項として記載されています。
- 人命に関わる緊急の事案については、直接110番通報をしてください
- 本窓口は相談機関ではないため、相談希望の場合はこちらに連絡してください
インターネットホットラインセンターの目的は、違法性・悪質性の高い情報を精査して、警察に情報共有するものです。
そのため、個人的な被害に関してインターネットホットラインセンターが解決してくれるわけではないため、その点のみ注意してください。
インターネットホットラインセンターの効果について理解しよう

この記事の結論をまとめると、
- インターネットホットラインセンターが世界各国と提携を結んでいる
- インターネット上に流通する情報で、違法性・悪質性の高いものを通報できる
- 実際に毎年多くの通報がされていて違法性のあるものも確認されている
- インターネットホットラインセンターは相談窓口ではない
- 個人が攻撃されたり緊急性のあるものに対しては警察等に通報する
ということが分かりました。
インターネットの普及とともに、インターネット上でのトラブルは年々増え続けているため、インターネットホットラインセンターの存在を知っておきましょう。
あなたの通報で、悪質なネットユーザーが摘発されたり、ウェブサイトが閉鎖に追い込まれたりするため、必要に応じて利用してみてください。